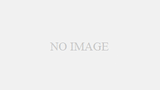出産に伴う経済的な負担をサポートする制度として、「出産育児一時金」と「育児休業給付金」があります。これらの制度を活用すれば、出産費用の軽減や育児中の生活費の確保が可能に。ただし、それぞれ申請手続きや必要書類が異なるため、しっかり確認しておくことが重要です。この記事では、出産一時金と育児休業給付金について、申請の流れと注意点をわかりやすく解説します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、健康保険に加入している人が出産した際に支給される制度で、原則として1児につき50万円(2023年4月改定)まで支給されます。多胎児の場合は人数分支給されます。
対象者
- 健康保険または国民健康保険の被保険者またはその扶養家族
- 妊娠12週(85日)以上での出産であれば流産や死産でも対象
申請方法
「直接支払制度」を利用する場合、医療機関が保険者に請求するため、基本的に本人の手続きは不要です。退院時に自己負担分(50万円を超えた分)だけ支払えばOK。
直接支払制度を利用しない場合
- 出産費用を全額自己負担
- 出産後、加入している保険窓口に「出産育児一時金支給申請書」を提出
- 病院発行の領収書・明細書を添付
- 後日、指定口座に給付金が振り込まれる
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児休業を取得した場合に、休業中の収入を補填する制度です。子どもが1歳になるまで(条件により最大2歳まで)受給可能です。
対象者
- 雇用保険に1年以上加入している
- 育児休業前の2年間に賃金支払いのあった月が12か月以上
- 育休中も会社に籍があり、休業期間中に働いていない
給付金額
- 育休開始から6か月間:賃金の67%
- 6か月以降〜:賃金の50%
申請の流れ
- 職場に育児休業の取得を申し出る(1か月以上前が望ましい)
- 会社が「育児休業給付金申請書」を作成
- ハローワークに会社が申請書を提出(原則2か月ごとに申請)
- 受給者本人の口座に給付金が振り込まれる
※自営業・フリーランスは対象外(代わりに「出産手当金」や「国民健康保険の給付」がある場合も)
申請時に必要な書類(共通)
- 母子手帳(出産日を証明)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座情報
- 保険証の写し(出産一時金用)
- 育児休業開始日の記録(育休給付金用)
注意点とスケジュール管理のコツ
- 育児休業給付金は職場の協力が不可欠。早めに相談を
- 書類の記入ミスや提出遅れに注意
- 手続きにはマイナンバーが必要なケースが多い
- 育児休業が延長になる場合はその都度申請が必要
まとめ
出産に関わる公的給付制度は、しっかり手続きを行えば家計を大きくサポートしてくれます。出産一時金は出産費用を補助し、育児休業給付金は生活の安定を支える心強い存在。職場や医療機関、保険者と連携しながら、早めに準備しておくことで安心して出産・育児を迎えることができます。わからないことがあれば、ハローワークや健康保険窓口に相談してみましょう。